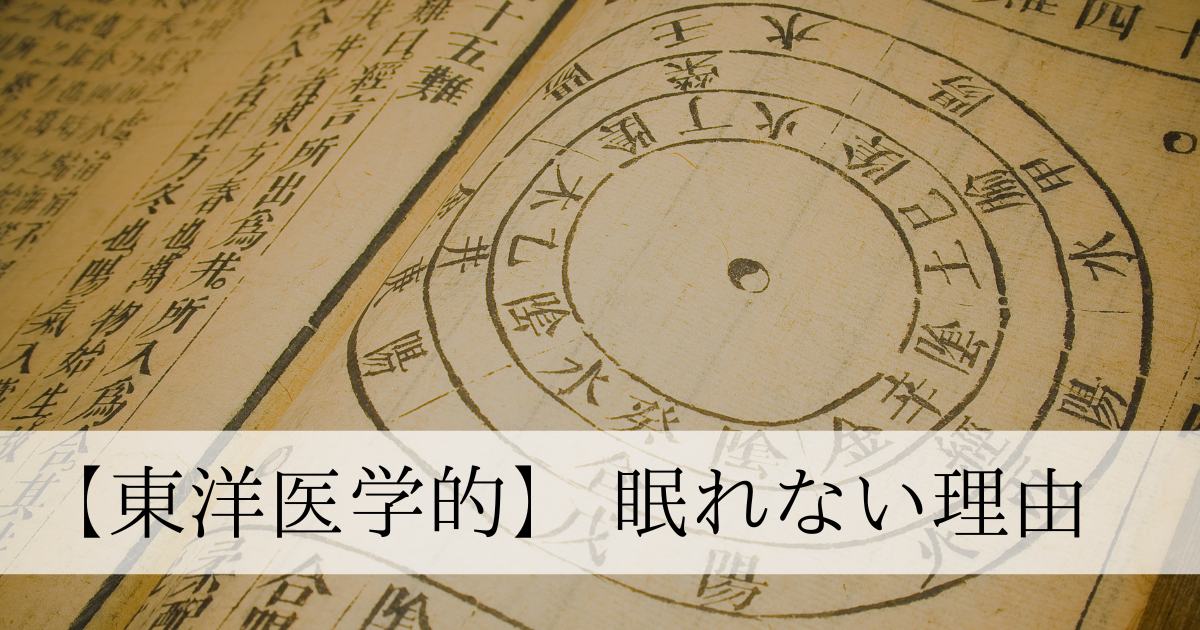「疲れてるのに寝つけない」「夜中に目が覚める」「眠ってもぐっすり感がない」——。
今や日本人の5人に1人が不眠というデータもあるほど、 眠りにまつわる悩みは年齢や性別を問わず多くの方が抱えるテーマです。
この記事では、東洋医学の視点から「不眠」の原因を読み解き、 眠り猫の鍼灸マッサージがどんな風にサポート出来るのかをご紹介します。
 眠り猫
眠り猫東洋医学って言っても難しく考える必要はないよ!
その前に、西洋医学(現代の医学)で考える不眠から説明するね。
現代医学でみる不眠とは?
現代医学において「不眠症」は、眠りに関する以下のような問題が1か月以上続き、日常生活に支障をきたしている状態を指します。
- 寝つきが悪い(入眠困難)
- 夜中に目が覚めてしまう(中途覚醒)
- 朝早く目が覚める(早朝覚醒)
- 眠った気がしない(熟眠障害)


不眠の原因には、ストレス・生活習慣・加齢・身体疾患・精神疾患・薬の副作用などがあり、さまざまな要素が関与していることも少なくありません。
不眠に対する治療は、不眠の原因や重症度によって異なりますが、一般的には次のような対処が行われます。
- 睡眠衛生指導(生活習慣の改善)
寝る時の環境や、睡眠を妨げる習慣を見直す - 認知行動療法(CBT-I)
睡眠日誌をつけるなど、睡眠改善のための考え方や行動をトレーニング - 睡眠薬などの薬物療法



この記事を読んでくれているあなた。
あなたの眠りのお悩みは①〜④のどれでしょうか。
1つじゃなくて2つ3つあったりする?
東洋医学でみる不眠とは?
東洋医学では、不眠は「体全体のバランスの乱れ」としてとらえます。
単に「眠れない」という現象だけを見るのではなく、
- 気・血・水の不足や滞り
- 五臓六腑の働きの乱れ(特に「心」「肝」「脾」「腎」)
- 陰陽バランスの崩れ など
全身の状態と心の状態、どちらも診ていくのが特徴です。


東洋医学では、陰陽バランス、気・血・水、五臓(肝・心・脾・肺・腎)の状態が整っていることが【健康】だと考えます。
生きている以上、常に変化して一定というわけではないけれど、多すぎたり、少なすぎたり、停滞することで、何かしらの不調が出てくるのです。
そのひとつが「不眠」という症状となって出てきているということです。



陰陽、気・血・水、五臓
ここら辺は東洋医学の基礎なので、改めて記事を書くので、もうしばらくお待ちください〜
東洋医学的 4つの不眠 ータイプ別の原因と特徴ー
それでは、東洋医学的な不眠の原因を4つに分けて紹介!
ひとつずつ見ていきましょう。
① 心脾両虚(しんぴりょうきょ)タイプ【虚証】
まず1つ目の不眠タイプは、特に女性に多い心脾両虚タイプです。
虚証なので、気血水や五臓のパワーなど、何かが足りていない、少ない、消耗しているような状態ですね。
心脾両虚の原因は?
思い悩みすぎ、疲労などにより「心」と「脾」が弱っているためと考えられます。
五臓の「心」と「脾」を世界一わかりやすく説明するとこんな感じ。
心脾両虚タイプになりやすいのは、繊細な人、ちょっと神経質な人、胃腸が弱い人に多いかもしれません。
心脾両虚の症状は?
眠りに関わる症状は、入眠困難、多夢(よく夢を見る)、中途覚醒。
他にも、忘れっぽい/元気がない/冷え性/顔色にツヤがない/胃のつかえ感などの症状が出ることも。
舌の特徴は?
舌は自分でチェックできる健康のバロメーター。
心脾両虚タイプの人の舌は、全体的に白っぽいのが特徴です。


② 心腎不交(しんじんふこう)タイプ【虚証】
2つ目の不眠タイプは、心腎不交タイプ。
心腎不交の原因は?
腎陰という生命力エネルギーの不足によって心火を抑えられず、神志(精神)が乱れるためと考えられています。
ここでは五臓の「腎」をわかりやすく説明します。
心腎不交タイプになりやすいのは、もともと体力があまり無い人、緊張しやすい人、過去に大病を患ったことがある人、貧血っぽい人、更年期の人や妊娠・出産の経験がある人に多いかもしれません。
心腎不交の症状は?
眠りに関わる症状は、入眠困難、多夢(よく夢を見る)、寝汗が多い。
他には、不安感が強い、動悸、のぼせやすい、耳鳴り、腰や膝のだるさなどの症状が出ることがあります。
舌の特徴は?
心腎不交タイプの人の舌は、赤みが強かったり、口が乾きやすかったりすることがあります。


③ 痰熱(たんねつ)タイプ【実証】
3つ目の不眠タイプは、痰熱タイプ。
3つ目と4つ目は実証なので、虚証と反対で、気血水や五臓のパワーなどが、多すぎる、停滞して詰まっているような状態ですね。
痰熱タイプの原因は?
暴飲暴食や水分代謝の低下によって「 痰熱」が生まれ熱が強くなり、精神に影響するためと考えられます。
痰熱タイプになりやすいのは、つい食べすぎてしまう人、味の濃い食べ物・ファストフードが好きな人、座りっぱなし・立ちっぱなしの時間が長い人、運動不足の人、便秘がちな人に多いかもしれません。
痰熱タイプの症状は?
眠りに関わる症状は、眠りが浅い、多夢(よく夢を見る)。
他には、胸苦しい感じ/赤ら顔/ニキビなどの肌荒れ/胃のもたれ/足のむくみ/便秘などの症状が出ることがあります。
舌の特徴は?
痰熱タイプの人の舌は、舌のコケが黄色っぽかったり、舌全体がボテっとむくんでいるかもしれません。


④ 肝火(かんか)タイプ【実証】
最後、4つ目の不眠タイプは、肝火タイプです。
肝火タイプの原因は?
イライラやストレスが強く、「 肝」 の機能が低下して熱が過剰になっていると考えられています。
五臓の「肝」を説明しますね。
肝火タイプになりやすいのは、家庭や職場などストレスが強い環境にいる人、ストレス発散や気分転換が苦手な人、感情の波が大きい人に多いかもしれません。
肝火タイプの症状は?
眠りに関わる症状は、入眠困難、眠りが浅い、中途覚醒。
他には、イライラしやすい/口の苦み/肋骨が張る/ため息が増えるなどの症状が出ることがあります。
舌の特徴は?
肝火タイプの人の舌は、赤みが強いのが特徴です。


不眠の悩みに対して鍼灸ができること
① タイプ別のアプローチ
鍼灸では「弁証(体質や状態の見立て)」に基づき、ツボを選んで施術を行います。
上記の4タイプに対して、それぞれ以下のようなアプローチが取られます。
心脾両虚タイプ
施術方針:養心健脾・補気生血
胃腸の調子を整えて、全身の巡りをよくします。
冷えがあれば温めていきます。
リラックス重視で、心と体を落ち着かせます。
心腎不交タイプ
施術方針:滋陰降火・交通心腎
生命力が宿ると言われる腹部や、冷えやすい手足を重点的に施術します。
このタイプは症状の改善にちょっと時間がかかります。
焦らず、コツコツと。
漢方薬との併用もオススメすることがあります。
痰熱タイプ
施術方針:清熱化痰・和胃安神
暴飲暴食してしまう人には、食べすぎるキッカケになっているストレスなどを突き止める、食生活の見直しをしていきます。
水分代謝や胃腸を活性化するツボを使って、巡りを改善。
運動不足が気になる人には施術中にストレッチなど軽い運動も一緒に行います。
肝火タイプ
施術方針:疏肝瀉火・寧心安神
頭部が熱っぽいことが多いので、頭部の鍼を増やして熱を散らすような施術をします。
しゃべることでストレス発散できる時は施術中にたくさん話したり愚痴ったりしてもらいます笑


② 症状だけでなく“眠れる体づくり”を
不眠とひとことで言っても、 その背景にはストレス・体質・内臓機能・生活習慣などさまざまな要素が複雑に関係しています。
眠れないという現象だけを見るのではなく、 「なぜ眠れなくなったのか?」を一緒に見つめ直し、 体質そのものを整えることで、“眠れる体”を育てていくのが鍼灸の特徴です。
特に眠り猫の基本は、頭だけじゃなく背中・お腹・手足・首など全身を見ます。
自律神経や五臓六腑のバランスを総合的に整えていく施術を行っています。





家でもできるお灸を使ったセルフケアや、ストレス発散法の提案などもしています。
より良い睡眠環境の見直しも一緒にやっていきますよ〜。
鍼灸はどんな人に向いている?
次のような人に鍼灸がオススメ!
- 日常生活に支障はないけれど、眠りの悩みを抱えている人
- 寝つきが悪い・眠りが浅い・夢が多いといった症状が長引いている人
- 睡眠薬をなるべく減らしたい・自然な眠りを目指したい人
- 精神的な不調(不安・緊張・うつ状態)から不眠が続いている人
ひとつでも当てはまる人は、鍼灸を試す価値アリです!
こればっかりは体験してみないと分からないので、お近くの鍼灸院に眠りの悩みについて相談してみてください。


重度の精神疾患や日常生活に著しい支障がある場合は、医療機関との併用をオススメしています。
まとめ|「不眠」に向き合うということ
睡眠は、美容にも心にも、そして免疫や回復力にとっても重要な“土台”です。
大切なのは「眠らせること」ではなく、「眠れる体を育てること」。
眠り猫の鍼灸は、あなたの体と心の声に耳をすませながら、 やさしく、じっくり整えていく時間を提供します。
眠れない日々に、終止符を打つための第一歩に。
ご相談はお気軽に!


女性専用サロンとして、眠り猫はいつでもあなたの“整う時間”をサポートします。
\ いつでも声かけてね🐈/